「宿題やった?」「あとでやる!」の押し問答、毎日くり返していませんか。
実は、やる気そのものより「仕組み」を整える方が早くてラク。
この記事では、我が家(小3と小2)の実体験をもとに、今日から使える宿題ルーティンを紹介します。準備5分・声かけは短く・親のイライラも減る方法です。

帰宅後15分は「クールダウン」—手洗いうがいをしたら、ゆっくり宿題に取り掛かる準備
学校から帰った直後はエネルギーが乱高下。
「おかえり~!さぁ宿題!」だと反発しやすいので、まずは15分程度のクールダウンを固定します。
例:手洗いうがい → ママとトーク → 「さぁ、そろそろ宿題の準備しようか」
ポイントは時間を決めること。キッチンタイマーやスマホのアラームを使い、鳴ったら宿題コーナーへ移動までをセットにします。
子どもも帰ってきてすぐ話したい事を話せた満足感もあり、「さぁ、やるか」と切り替えやすいです。
話の続きがあったとしても、「宿題終わったらまた聞かせてね!」とポジティブに声掛けすると◎。
宿題は一気にやった方が後がラクと思わせる。20分~30分、学年に合わせて調整を。
低学年は集中の器が小さいのが普通。だけどダラダラしていたらいつまでも終わらない悪循環に陥ります。
学年×10分を目安に宿題を一気に終わらせる方針で、とにかくその時間は机に向かう習慣をつけさせましょう。
うちも低学年のうちはなかなか難しかったけど、5分ごとに宿題ノートをのぞき込んで、出来ているところを褒める(例:ここの字すごくきれいだね!とか)と、やる気持続に一役買ってくれます。
ちなみに勉強を進んでやる子は数時間でも自ら机に向かうことが出来るようです(甥っ子がそうです)が、その場合は長時間同じ姿勢になることで視力低下や肩の凝りにつながることもあるので適度に休憩を挟みながらやるのが良いですね。
「やる順番」は子どもに決めさせる—選択肢メニューで主体性アップ
指示だけだとだらけてしまいがちなので、宿題のやる順番は選べるメニューにします。
- ① 計算 → ② 音読 → ③ 漢字
- ① 音読 → ② 漢字 → ③ 計算
「今日はどっちにする?」と二択にすると、決断疲れが出ません。自分で決めた順番は崩れにくく、集中も続きやすいです。
ドリルなら、ページを開いて(どのような宿題なのか明確にして)「どっち?」と聞いてあげると「あ、今日は簡単なやつだ」「難しいのからやっちゃおうかな」など、自分で考えて取り組む姿勢も見られるし、子どもの得意不得意も見つけやすくなります。
リビングなど、親の見える範囲にに“宿題ステーション”をつくる—道具はワンボックス集約

探し物は集中を奪う最大の敵。道具は1カ所に全集約します。
- 筆記具(鉛筆3本/消しゴム/赤ペン)
- ものさし・のり・はさみ
- 時計やキッチンタイマー
ワンボックスで「出す→使う→戻す」を固定化。机は親の目が届くリビングの端がベスト。
100円ショップに売っているカゴでも十分ですし、子どもと一緒に小さな段ボールや厚紙で作っても良いですね。
親の声かけはルール化—先に承認→短い具体指示→終わったら称賛
関わり方は型にしておくとラクです。
- 承認:「帰ってきたね、今日もおつかれ!(掛け算むずかしかった?リコーダーできた?などその日の勉強を簡単に振り返り)」
- 具体指示:「じゃあ今日の宿題準備始めようか、ノート(ドリル)出してね。今日は●ページかな~どっちからやる?計算?音読?」
- 見守り:「すらすら読めてるね!」「今の漢字の書き順、ばっちりだったね!」
- 称賛:「今日もやり切れたね。さすが!」
注意は行動の事実に限定(「字が汚い」ではなく「マスからはみ出した分だけ直そう」など)。
つまずきサインの見つけ方—量・難度・環境の3点を微調整
進まない日は怠けではなく設計が合っていないサイン。
- 量:学年×10分で区切れる量でない場合は小分けにする
- 難度:最初は一番簡単な問題から。成功体験で勢いをつける
- 環境:テレビは消す、席を窓から遠ざける、椅子の高さを合わせる
環境を整えて、「どこで」「なにで」つまずいているのか確認してみましょう。
とはいえ量は学校が決めることがほとんどだし、簡単な問題からやらせようとしても子どもの性格で「1番から順番にやっていきたい!」と言われることもよくあります。
そんなときは、親の横並び学習(同じ机で各自の作業をする)が効きます。
うちは子供たちはリビングとなりの部屋に学習机を置き、その隣にママの作業用机(テレワーク用のパソコン)をおいています。
明日から使える「宿題ルーティン」チェックリスト
- 帰宅後15分程度のクールダウンで子どもとコミュニケーション
- 学年×10分を目安に集中できる環境をつくり、「宿題はこのタイミングでやるものだ」と習慣づけ
- 二~三択の順番メニューから子どもが選ぶ
- ワンボックスの宿題ステーションを作る
- 承認→具体指示→見守り→称賛の声かけルール
まとめ:仕組みが整えば「やる気待ち」は卒業できる
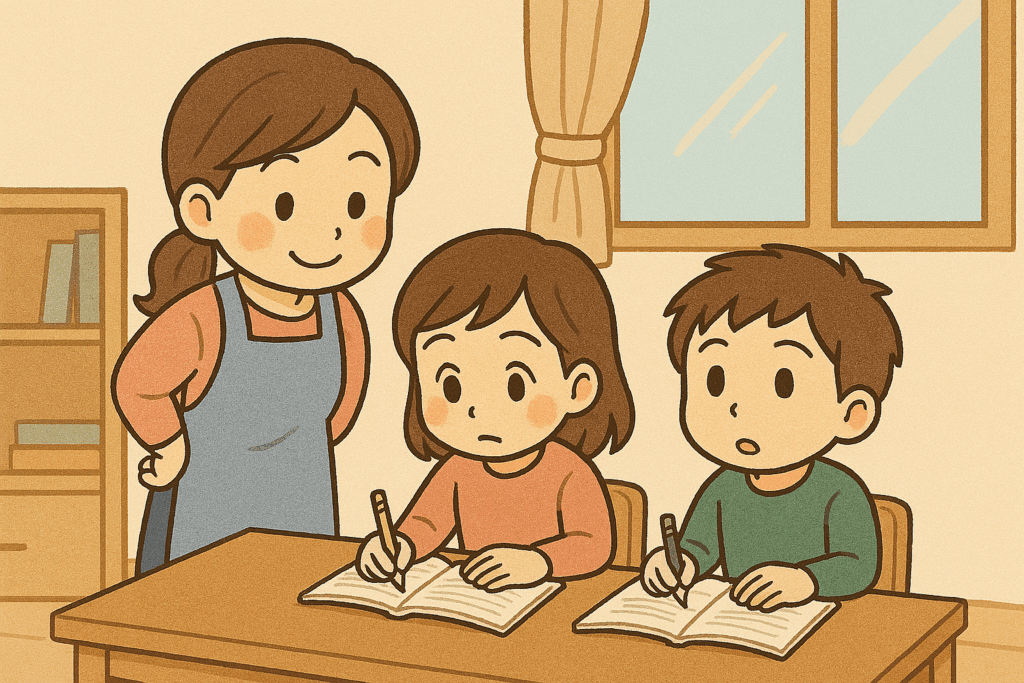
宿題は根性ではなく設計の勝負。クールダウン→時間で区切る→選択の自由→道具の集約→声かけの型、の5点をそろえれば、決まった時間で切り替えてエンジンがかかる子に変わります。
完璧を目指さず、明日は1つだけ導入してみましょう。


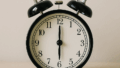
コメント